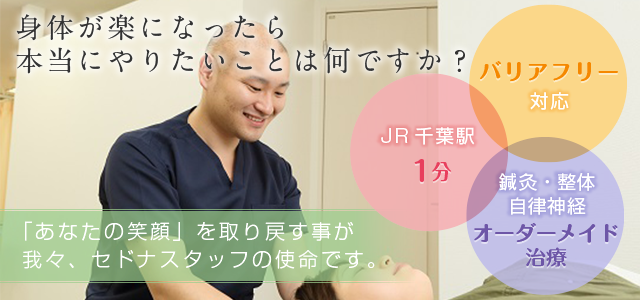
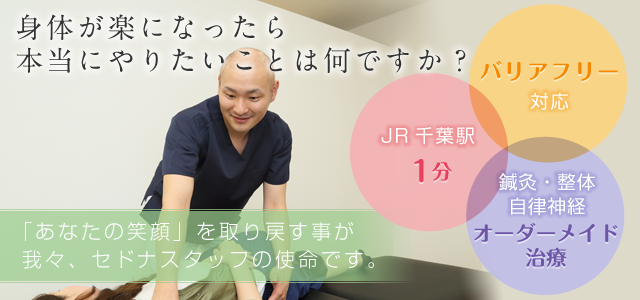

こんにちは!セドナ整骨院千葉駅前院の佐々木です。
今月は鍼灸と逆子についてお話させて頂きたいと思います。
妊娠後期に入り、「赤ちゃんが逆子だと言われた…どうしたらいいんだろう…」と不安になる妊婦さんは少なくありません。一般的に妊娠30週以降になっても胎位が骨盤位(逆子)の場合、自然に頭位に戻る確率は徐々に低下するとされています。多くの妊婦さんは妊娠30~32週ごろに逆子の診断を受け、診断後から逆子体操や外回転術(ECV)を試みますが、それでも戻らないケースも一定数あります。
そんな中、近年注目されているのが鍼灸による逆子の矯正です。特に「至陰(しいん)」というツボへのお灸(灸治療)が逆子の改善に効果的だとする研究が報告されています。
今回はまず、逆子とは何か、定義や種類について学んでいきましょう。
◎逆子とは?
逆子(さかご)とは、医学的には「骨盤位(こつばんい)」と呼ばれる胎児の胎位の一種です。通常、妊娠後期には胎児の頭が母体の骨盤の方向に向く「頭位(とうい)」になりますが、逆子の場合は胎児の臀部や足が子宮口の方を向いたままの状態となります。
妊娠初期から中期にかけては、胎児が活発に動くため、一時的に逆子になることは珍しくありません。しかし、妊娠30週を過ぎると胎児の動きが制限され、逆子のまま固定される可能性が高まります。一般的に、妊娠30週で約15%の胎児が逆子ですが、妊娠34週には7~8%、最終的に外回転術が成功しなかった場合、分娩時には約3~4%の割合で逆子となると報告されています。
◎逆子の分類(種類)
逆子にはいくつかの種類があり、胎児の向きや足の位置によって分類されます。
・単殿位(たんでんい)
胎児のお尻が子宮口の方を向いており、足は上方(母体の頭側)に伸びている状態
逆子の中で最も一般的なタイプであり、約50~70パーセントを占める
経膣分娩が可能な場合もあるが、リスクが高いため帝王切開となるケースが多い
・全殿位(ぜんでんい)
胎児のお尻が子宮口に向いているが、足があぐらをかいたような姿勢になっている
頭位への回転が難しいことが多い
・足位(そくい)
胎児の片足または両足が子宮口に向いている状態
分娩時に足から先に出てしまうため、帝王切開が推奨される
・膝位(しつい)
胎児が膝を折り曲げた状態で膝が子宮口の方向に向いている
まれなタイプだが、分娩時のリスクが特に高いため、ほぼ帝王切開となる
◎逆子の原因
逆子の原因は完全には解明されていませんが、以下の要因が関係していると考えられています。
・羊水が多すぎる(羊水過多)場合、胎児が過剰に動きやすくなる。反対に羊水が少ない(羊水過少)と胎児の回転が制限され、逆子のまま固定されやすい。
・双角子宮や中隔子宮などの子宮形態異常がある場合、胎児が自由に回転できず逆子になりやすい。これらの異常は超音波検査やMRIで診断される。
・前置胎盤や低置胎盤など胎盤の位置が低い場合、胎児が頭位に回転するスペースが制限されるため、逆子の原因となる可能性がある。
・染色体異常や神経系の発育異常(無脳症や水頭症など)がある胎児は、頭位への回転が困難になることがある。
・双子や三つ子などの多胎妊娠では、子宮内のスペースが限られるため、一方または両方の胎児が逆子になる確率が高い。
これらの要因が複雑に絡み合い、逆子が発生すると考えられています。
◎逆子のリスク
逆子の場合、多くの病院では安全を考慮し帝王切開を推奨しています。特に足位や膝位のように胎児の足や膝が先に出る形の逆子は、経膣分娩のリスクが高いため、ほぼすべてのケースで帝王切開となります。
一方、単殿位や全殿位の場合、医師の判断によっては経膣分娩が可能とされることもありますが、娩出時に胎児の頭が引っかかる可能性があるため、慎重な管理が必要です。
・胎児への影響
逆子のまま分娩を迎えると、胎児の頭が最後に出るため、十分な酸素を供給できない時間が長くなることがあります。そのため、低酸素状態や分娩遅延による影響が懸念されます。また、逆子の状態が長く続くことで、股関節脱臼(発育性股関節形成不全)を発症するリスクが通常の頭位の赤ちゃんよりも高くなることが知られています。そのため、逆子だった赤ちゃんは出生後に股関節のエコー検査などを受けることが推奨される場合があります。
今回は「逆子の定義と種類」についてお話させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?
次回は「逆子に対する鍼灸治療における臨床研究、またそのレビュー」についてお話させていただきます!
最後までお付き合いいただけますと幸いです。
セドナ整骨院・鍼灸院・カイロプラクティック 千葉駅前院 佐々木