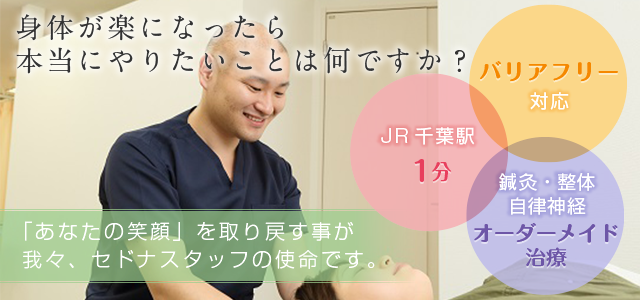
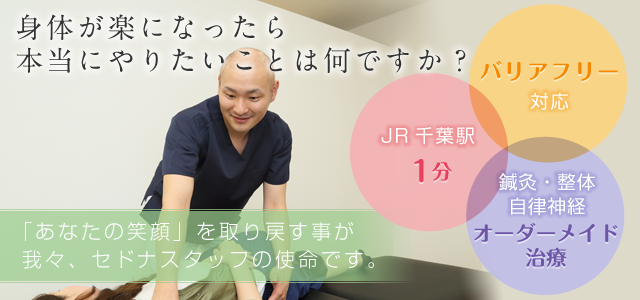

こんにちは!セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院の佐々木です。
今回は「鍼灸治療における臨床研究、またそのレビュー」についてお話させて頂きます。
◎鍼灸治療における糖尿病への効果に関する臨床研究とレビュー
近年、糖尿病の管理において、補完代替医療の一環として鍼灸治療が注目されています。
特に、鍼灸が血糖値の調節、糖尿病性末梢神経障害(DPN)などの合併症の緩和、さらにはストレスや炎症の抑制を通じて、患者の生活の質(QOL)を向上させる可能性があるとする研究が増えています。こうした動きの中で、科学的根拠を積み上げるため、鍼灸治療を用いた臨床研究やレビューが国内外で活発に行われています。今回は、これらの研究の中から鍼灸治療の効果についてお話していきます。
◎糖尿病に対する鍼灸治療の臨床研究
研究例1:血糖値の管理における鍼灸の効果 Liu et al.(2018年)のランダム化比較試験(RCT)では、2型糖尿病患者を対象に鍼灸が血糖値管理に与える影響を検討しました。
この研究では、対象者を以下の2群に分けて8週間治療を行いました。
治療群:標準的な薬物療法(メトホルミン)に加えて、週3回、主要な経穴(例:足三里、合谷、三陰交など)に鍼治療を実施。
対照群:薬物療法のみ。
治療後、治療群では空腹時血糖値(FPG)が平均15mg/dL以上低下し、HbA1c(糖化ヘモグロビン)も0.7%減少しました。一方、対照群ではこれらの数値に有意な変化が見られませんでした。また、患者からは治療後の疲労感や睡眠の質の向上が報告されており、鍼灸が血糖値の調節のみならず、全体的な体調改善にも寄与した可能性が示されました。
この研究は、鍼灸が血糖値を改善する補完療法として有望である一方で、治療の具体的なメカニズムを解明するさらなる研究の必要性を強調しています。
研究例2:糖尿病性末梢神経障害(DPN)への鍼灸の応用
Sun et al.(2019年)の研究では、糖尿病性末梢神経障害(DPN)患者120名を対象に、鍼灸が神経痛や感覚異常の改善にどの程度効果を持つかを評価しました。
治療群:週3回、12週間にわたって電気鍼を含む鍼灸治療を実施。使用経穴は主に太衝、三陰交、足三里など。
対照群:一般的な神経再生療法(ビタミンB12の投与)を実施。
結果として、治療群では疼痛スコア(Visual Analog Scale, VAS)が平均40%以上改善し、感覚機能の回復(触覚および温度感覚の改善)が認められました。さらに、神経伝導速度も有意に向上し、末梢神経の再生や修復に鍼灸が寄与している可能性が示されました。一方、対照群ではこれらの改善が限定的でした。
この研究は、鍼灸がDPNのような難治性の合併症に対する補助療法として注目されるべきであることを示唆しています。
◎システマティックレビューとメタアナリシス
個別の臨床試験を超えて、鍼灸の効果を統合的に評価するため、近年システマティックレビューやメタアナリシスが数多く実施されています。
メタアナリシスの例:血糖値と鍼灸治療 Zhao et al.(2021年)のシステマティックレビューは、糖尿病患者を対象に行われた18件のRCTを分析し、鍼灸が血糖値管理や合併症の緩和に与える効果を評価しました。
主要成果: 空腹時血糖値(FPG)は鍼灸治療群で平均15mg/dL低下。HbA1cは平均で0.6%減少。血糖値だけでなく、炎症性マーカー(C反応性タンパク、TNF-αなど)の有意な減少も確認。
限界点: 一部の研究でサンプルサイズが小さいことや、治療方法の不統一が問題視されました。さらに、偽鍼(シャム鍼)を用いた試験の不足も課題として挙げられました。
◎鍼灸が糖尿病に与える効果のメカニズム
鍼灸が糖尿病患者の症状改善に寄与する可能性が示唆される一方で、その効果を裏付ける生理学的メカニズムはまだ完全には解明されていません。しかし、以下の仮説が広く支持されています。
1. 自律神経系の調節 鍼灸は交感神経の過剰な活動を抑制し、副交感神経を刺激することで、インスリン分泌やグルコース代謝を改善すると考えられています。特定の経穴刺激が迷走神経の活性化を誘発し、血糖値の低下をもたらす可能性が示されています。
2. 抗炎症効果 慢性炎症は糖尿病の病態形成に深く関与しています。鍼灸が炎症性サイトカイン(TNF-αやIL-6など)の産生を抑制し、炎症反応を緩和することで、インスリン感受性を改善する可能性が示唆されています。
3. ストレス軽減 鍼灸によるリラクゼーション効果がコルチゾール(ストレスホルモン)の分泌を抑え、血糖値の安定化に寄与するという報告もあります。
◎鍼灸治療の課題と今後の展望
課題1:研究デザインの改善 多くの研究で盲検化の不備やサンプルサイズの不足が課題として挙げられています。特に、偽鍼(シャム鍼)を用いた対照試験が、効果を正確に評価する上で重要です。
課題2:経穴の標準化 経穴や治療手法が研究ごとに異なるため、結果の再現性に欠ける場合があります。統一された治療プロトコルを策定することが求められます。
課題3:長期的効果の検証 現在の研究は短期間の効果に焦点を当てたものが多く、鍼灸治療の長期的な安全性や有効性についてのデータが不足しています。
今後の展望 :鍼灸は糖尿病の標準的な治療法を補完する有力な手段として、さらに発展する可能性があります。特に、個別化医療(=体質や病気の特徴に合った治療を行うこと)の観点から、患者の病態や体質に応じた鍼灸プロトコルの最適化が期待されています。
糖尿病に対する鍼灸治療は、血糖値管理や合併症緩和において有望な補完療法として注目されています。近年の臨床研究やメタアナリシスは、鍼灸が糖尿病管理に一定の効果を持つことを示唆していますが、研究デザインや標準化の不足といった課題も残されています。今後、高品質な研究を通じて鍼灸の有効性と安全性が確立されることで、糖尿病治療における選択肢がさらに広がることが期待されます。 糖尿病治療の目標は、血糖値を良好に維持し、合併症のリスクを低下させることにあります。HbA1cの目標値は一般的に 7.0%未満 とされていますが、高齢者や合併症を有する患者では、個別の目標値が設定される場合があります。 治療の基本は、食事療法、運動療法、薬物療法(経口薬やインスリン)であり、これらを組み合わせて血糖コントロールを行います。特に合併症の予防や患者の生活の質(QOL)を向上させることが重視されています。
ここまでは各研究テーマに沿ったお話になりました、以下は臨床に携わる私の所感です。 患者様と接させて頂く中で糖尿病の治療は血糖値管理だけでなく、合併症の予防や患者の生活の質(QOL)の向上も大切なのだと感じ、鍼灸師としてそこにアプローチをかけることを目指しています。一部の患者様は薬物療法だけでは血糖値のコントロールが不十分な場合があり、補完医療や代替医療が選択肢として取り上げられることがあります。鍼灸治療はその一つです。
私達が行う鍼灸は基本的に東洋医学に基づく治療法であり、体内の「気(エネルギー)」の流れを整えることで、自然治癒力を高め、病気を改善するとされています。 気の流れ?と聞くと少し胡散臭く聞こえるかもしれませんが、私達は日常の中から「なんとなく雰囲気が悪い」「嫌いな人がいて気が重い」「あの人は良く気が配れる人だ」「気のせいかもしれないが誰かに追われている気がする」といったように、無意識に「気」という言葉を使っています。 気は見える物ではないですが、確実に私達の生活に根付き、そしてそこに存在する物といっていいのではないかと考えます。 私達鍼灸師は細い針を体の特定のツボ(経穴)に刺し、気の流れを調整します。 灸治療では、もぐさを燃やして熱刺激を与えます。これらは、神経系や血流、免疫機能に影響を与えると考えられています。 現代医学的には、鍼灸が神経伝達物質やホルモンの分泌を調節し、鎮痛や抗炎症効果をもたらす可能性があるとされ、糖尿病の症状や合併症への効果が期待できます。 現在西洋医学のように症状に合わせて薬の種類が増えていくという物ではなく、人の身体の状態をみて鍼を刺す経穴や施術を決めて参ります。次回はこちらの内容のついて詳しくお話させて頂きたいと思います。
以下は今回のまとめです。
◎鍼灸治療と糖尿病の関係まとめ
① 血糖値の管理
いくつかの研究では、鍼灸が血糖値を改善する可能性が示唆されています。例えば、ある臨床研究では、鍼灸治療がインスリン感受性を向上させ、血糖値を低下させる効果が確認されています。この効果は、鍼灸が副交感神経を活性化し、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制することで実現していると考えられます。 動物実験では、特定のツボ(例えば胃経の足三里、脾経の三陰交)への鍼刺激が血糖値を低下させるメカニズムが報告されています。この現象は、β細胞の機能改善や炎症の軽減によるものとされています。
② 糖尿病の合併症の改善
糖尿病の有名な合併症として神経障害、腎障害、網膜症という三大合併症が挙げられます。 この中でも特に糖尿病性末梢神経障害(DPN)は、患者に痛みやしびれを引き起こし、日常生活に大きな影響を与えます。鍼灸治療は末梢血管の拡張、神経の過剰興奮の抑制を引き起こし、神経障害の症状を軽減する可能性があります。近年では2020年に発表されたメタアナリシスによると、鍼灸治療は糖尿病性神経障害の疼痛緩和に有効であるとされました。この研究では、鍼が血流改善や神経伝達物質の調整を通じて、神経障害の症状を軽減することが示されており、伝統的な東洋医学に再現性のある西洋医学の良い所が合わさった一例ではないかと感じます。
③ その他の効果
鍼灸治療の刺激は末梢の神経から脊髄に入力され、刺激は脳・脳幹部へ電気刺激として伝えられて中枢神経に良い影響を及ぼす事が知られています。とくに鍼灸治療は痛みを伴うストレスの軽減や睡眠の改善にも役立つとされ、これが糖尿病の管理に間接的に貢献します。ストレスは血糖値を上昇させる要因となるため、鍼灸によるリラクゼーション効果は治療の補助として重要です。
④ 鍼灸治療の限界と注意点
一方で、現在西洋医学が万能でないように東洋医学、鍼灸治療にもいくつかの課題があります。まず、治療効果には個人差があり、すべての患者に有効とは限らないという事です。糖尿病に限ったことで言えば糖尿病の重症度や合併症の進行状況によってもその効果が異なるため、適切な診断と専門家による施術が合わせて必要となります。 さらに、現在でも研究が進んでいるとは言え、鍼灸治療は薬物療法の完全なる代替ではなく、あくまで補助的な役割を果たすものである点に留意する必要があります。軽度の方で医師からの同意を得て、施術を行っている方も多くご来院されております(運動療法・食事療法などで対応可能な患者様が多い印象です)、血糖値のコントロールが不安定な場合には、鍼灸治療のみでの管理は推奨されませんのでお気を付けくださいませ。
⑤ まとめと今後の展望
鍼灸治療は、糖尿病の補完医療として一定の可能性を十分に示しています。特に血糖値の調整や神経障害の症状緩和、ストレス軽減といった側面で有益な効果が期待できます。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、エビデンスに基づく適切な治療法の選択と、医師や鍼灸師との連携が重要です。
今週も読んで下さりありがとうございました。 今回は「鍼灸治療における臨床研究とそのレビュー」についてお話させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか? 鍼灸は古くからの伝統療法でありながら、現代の科学の力によってその効果が再評価されています。臨床研究の進展により、鍼灸がさまざまな症状に対して有効であることが示されてきました。今後も鍼灸の研究が進むことで、より多くの人々がその恩恵を受けられることを私は期待しています。皆さんも鍼灸に興味を持ち、実際に体験してみることで、その効果を実感していただければと思います。
来週は・・・今回の内容を踏まえ、「鍼灸治療の効果と効能、使われる経穴」に関してお話させて頂きます。どうぞ付き合い頂けますと幸いです。
セドナ整骨院・鍼灸院・カイロプラクティック 千葉駅前院 佐々木